ベランダは蜂が寄って来る可能性が高い場所です。蜂にとって好条件がそろっている場合が多いため、寄って来る蜂を放置していると巣作りされるリスクもあります。
本記事では、ベランダに蜂が寄って来る理由と予防策、巣ができてしまった場合の対処法を詳しく解説します。また、ベランダに巣を作る蜂の種類やアパート・マンションなどの集合住宅の場合の対応も解説するので、ぜひ参考にしてください。

目次
ベランダに蜂が来る3つの理由

ベランダは蜂が好む条件がそろいやすい場所です。具体的には次の3つのポイントがあげられます。
3つのポイント
・甘い香りがするから
・雨風を避けられる場所があるから
・ひと休みしやすいから
甘い香りがするから
花の蜜や果実の汁をエサとする蜂は、次のような甘い香りがする場所をエサ場と認識します。
甘い香りの例
・花のプランター
・ジュースの飲み残し(空き缶等)
・甘い香りの柔軟剤(洗濯物)
・アロマ・お香
とくに、多くの蜂が活発な4~10月は、甘い匂いを外に出さないことをおすすめします。できる限りベランダから撤去し、アロマやお香を室内で楽しむときは窓を開けないようにしましょう。
雨風・日光を避けられる場所があるから
蜂は雨や風で飛びづらくなるほか、日光による温度上昇で活動が低下するため、雨風・直射日光を避けられる場所を好んで巣作りします。ベランダでは次のような場所が巣作り条件と合致します。
巣作りの条件と合致する
・軒下
・テーブルや椅子の下
・荷物・箱の隙間
・室外機の裏・中
・シャッターや雨戸の戸袋の中
・外壁の亀裂の中
開放的な場所や狭い場所はアシナガバチに好まれやすく、外壁の隙間から侵入できる閉鎖的な場所はスズメバチやミツバチが好みます。置いてある物が多いと、蜂の営巣を発見しづらくなるため、定期的に片づけることをおすすめします。
ひと休みしやすいから
狩りや採蜜の途中の休憩場所としてベランダが選ばれることもあります。突然の雨や強い風、日差しが強い日の休憩場所として好条件だからです。一時的な休憩の場合、洗濯物にしがみついていることもあるため注意しましょう。気づかずに取り込んでしまうと、室内で家族やペットが蜂に襲われる危険があります。
また、多くの蜂は夜に活動を停止するため帰巣しますが、遠征していて日没までに巣へ帰れなかった場合は、翌日の日の出まで休むこともあるようです。
ベランダで巣作りさせないための4つの予防策

蜂を寄り付かせないために、次の4つのポイントを意識して取り組みましょう。
ベランダの予防策
・花のプランター・空き缶ゴミを撤去する
・柔軟剤を無香料のものに変える・室内干しにする
・蜂用の忌避剤を散布・設置する
・防虫ネット・蚊帳を取り付ける
花のプランター・空き缶ゴミを撤去する
甘い香りがするものは撤去するのがベストです。花のプランターはできる限り室内に入れましょう。空き缶やペットボトルはしっかり洗い、ゴミ袋で密封した上で蓋つきのゴミ箱に入れるなど匂い漏れを防ぐと蜂予防の効果があります。
なお、室内に入れられない場合やゴミ箱の設置が難しい場合は、後述の忌避剤や防虫ネットの使用がおすすめです。
柔軟剤を無香料のものに変える・室内干しにする
多くの蜂が活動する4~10月は柔軟剤を無香料のものに変えるのがおすすめです。蜂の営巣開始は4~6月、狩りや採蜜は6~10月が活発であるため、この時期に甘い香りをベランダ周辺で漂わせないようにしましょう。とくに、蜂が多いエリアでは注意が必要です。
11月から翌3月までは働き蜂が死滅し、女王蜂は冬眠に入る期間なので、気にする必要はありません。
蜂用の忌避剤を散布・設置する
甘い香りがするものを撤去しても、ベランダが雨風・日光の影響を防げる場所には変わりないため、蜂が多いエリアの場合は忌避剤も使いましょう。忌避剤には次のような選択肢があります。
忌避剤の種類
・蜂用の忌避スプレー
・木酢液
・ハッカ油
最も効果が高いのは、蜂駆除成分(殺虫成分)が含まれた忌避スプレーです。殺虫成分が残存するタイプであれば、寄ってきた蜂を駆除できます。軒下や室外機周辺など、蜂が狙いやすい場所にしっかりスプレーしておきましょう。ただし、室外機の中に噴霧するのはNGです。忌避スプレーが付着した場所がショートし、室外機が故障するリスクがあります。
木酢液は炭を作る際に出た成分でできた、蜂が嫌う臭いのする液体です。蜂の忌避剤として使う場合は2~5倍に希釈して使用します。詳しくは木酢液の選び方を参考にしてください。ただし、酸性で金属を腐食させるため、室外機周辺や金属製の窓のサン、手すり周辺には向きません。
ハッカ油は忌避スプレーや木酢液に比べると効果が低いものの、小さな子供やペットのいる家庭でも安心して使いやすいアイテムです。ハッカ油と水を混ぜたものを、蜂が寄り付きそうな場所に散布しておきましょう。
防虫ネット・蚊帳を取り付ける
蜂が通り抜けられないほど目の細かい防虫ネットや蚊帳を取り付ければ、営巣・寄り付きを防げます。防虫ネット・蚊帳はECサイトやホームセンターで購入可能です。ただし、ベランダの軒下から吊り下げる場合は脚立を使用する必要があるため、転落事故を防ぐために、必ず次の準備をおこないましょう。
転落事故を防ぐ条件
・命綱をつける
・2人以上で取り組む(脚立を支える役割)
これらの条件が整わない場合は、プランターや荷物などを囲える低所用の防虫柵などを検討しましょう。
こちらもCHECK
-

-
蜂・蜂の巣は自分で駆除できる?対応可能な種類・時期・方法を徹底解説
蜂の巣が近くにできると、できる限り早く駆除したいものです。コストを抑えるために、自分で駆除したいと考えることもあるでしょう。しかし、駆除方法さえ知っていればどんな蜂でも駆除できるというわけではありませ ...
続きを見る
ベランダに巣を作る蜂の種類

ベランダに巣を作りやすい蜂は次の4種類が代表的です。可能性が高い順に並んでいます。
ベランダに巣を作る主なハチ
・アシナガバチ
・スズメバチ
・ミツバチ
・ドロバチ
アシナガバチ


アシナガバチは開放的な場所を好む蜂です。ベランダの軒下や荷物の隙間などに巣を作ります。ただし、巣が最大でも20cmと小型であるため、戸袋や室外機の中などのやや閉鎖的な場所にも営巣可能です。
アシナガバチ巣は傘のような形で、直径は最大でも20m程度、育房がよく見えるつくりをしています。色はアシナガバチの種類によって違いがありますが、白・灰色・茶色が中心です。
攻撃性・毒性ともに中程度で、スズメバチほどの危険性ではありませんが、刺されれば痛みや腫れ、アナフィラキシーショックのリスクがあります。自分で駆除する場合は後半の「ベランダの蜂は自分で駆除できる?5つのポイントで判断しよう」をご覧ください。
スズメバチ


スズメバチはスズメバチ科スズメバチ属の総称で、攻撃性が低い蜂も属していますが、日本国内最強のオオスズメバチを含め、危険性の高い蜂が多い種類です。屋根裏や床下、木のうろなどの閉鎖的な場所を好んで営巣します。しかし、近隣に最適な場所がない場合は、比較的開放的な軒下にも営巣することがあるため要注意です。
巣は初期段階では提灯型あるいはとっくり型、ピークを迎える頃には球型に変化します。マーブル模様や波模様の球型の巣を見つけたら、スズメバチと見て間違いないでしょう。
スズメバチの巣は放置すると60cmを超えることもあり、攻撃的な働き蜂の数が1,000匹以上になることもあるため危険です。女王蜂だけが営巣を始めた最初期の段階であれば自分でも駆除できますが、働き蜂が出現したら自分で駆除せずに蜂駆除業者に依頼しましょう。
ミツバチ


国内に生息しているのは野生のニホンミツバチと養蜂のセイヨウミツバチの2種類です。セイヨウミツバチの場合は、ベランダの花に採蜜に来ることはあっても、営巣することはありません。野生のニホンミツバチであればベランダに営巣する可能性はありますが稀です。
ミツバチは毒針を刺すと死んでしまうため、刺激しない限り刺してくることはありません。1匹2匹を見かけただけなら、放っておきましょう。頻繁に寄ってくるようであれば、忌避剤を散布すれば防げます。
なお、ミツバチの分蜂のシーズンは大群のミツバチがベランダにとまって休むことがあります。引っ越し途中の一時的な滞在なので、慌てずに見守っていれば去っていくはずです。ただし、外壁の隙間から屋根裏などへ侵入できる場合や、木箱などがおいてあると営巣されることがあります。
4~6月の分蜂シーズンに入る前に、外壁の隙間をパテで埋めたり、木箱を撤去したりといった対策を講じておきましょう。
ドロバチ


ドロバチは単独行動を好む蜂で、働き蜂が活動するコロニーは形成しません。直径1~4cm程度の泥の塊のような巣を作り、卵を産みつけると去ります。巣作りの場所は外壁や閉じたままのシャッターの側面などです。高圧洗浄機やブラシでさっと落とせるほか、働き蜂もいないため安全に駆除できます。
攻撃性はほとんどなく、営巣のために外壁や柱を傷つけることもないため、放っておいても問題ない蜂です。ただし、ドロバチ科の中でも黄色~オレンジの模様が目立つスズバチの場合は、ベランダの外壁の隙間から侵入して屋根裏に作ることもあるようです。ドロバチが持ち込む湿気で柱や梁が腐食する可能性があるので、外壁の隙間はパテで埋めておきましょう。
ベランダの蜂は自分で駆除できる?4つのポイントで判断しよう

ベランダに蜂の巣ができたとき、早期発見であれば自分で駆除できる可能性があります。しかし、次の4つのポイントすべてに該当した場合のみです。
4つのポイント
・蜂の巣の大きさが直径10cm未満
・手が届く高さ、場所にある
・夜に時間を確保できる
・必要なアイテムをそろえられる
蜂の巣の大きさが直径10cm未満
巣の大きさが10cmを超えると働き蜂が成虫になっている可能性が高いため、刺されるリスクが高まります。アシナガバチであれば数匹の働き蜂がいても安全を確保しながら駆除できる可能性はありますが、スズメバチの場合は危険です。
スズメバチの場合は、女王蜂単体が営巣を開始した段階であれば比較的安全に駆除できるので、着手する前に巣の周辺を飛び交う蜂がいないかを確認しましょう。
なお、ミツバチの場合は女王蜂が単体で営巣することはまずありません。大量の働き蜂とともに移動(分蜂)して営巣するためです。逆にドロバチの場合は、巣は最大でも4cm程度で働き蜂は存在しないので、いつでも安全に駆除できます。
手が届く高さ・場所にある
自分で駆除できるのは、脚立などを使わずに手が届く場所に限ります。脚立を使用すると万が一襲われたときに逃げづらいため、刺されるリスクが高まるからです。
また、室外機の中や入り組んだ場所など、手が届きづらい場所・巣の全体像を視認できない場所の駆除は避けましょう。予想外に肥大化していたり、駆除剤を散布しても回りきらなかったりして、駆除しきれなかった蜂に刺されるリスクがあります。
夜に時間を確保できる
駆除の時間帯は夜がおすすめです。ほとんどの蜂は日没後2~3時間で活動が低下するため、襲われるリスクを低減できます。ただし、モンスズメバチは夜行性なので、深夜~日の出前までに作業する必要があります。
夜間に視界を確保するためにライトを使いたい場合は、赤いセロファンをつけた懐中電灯などで、赤色の光源にしましょう。赤は蜂が視認できないため、光によって目を覚まさせてしまうリスクを軽減できます。
必要なアイテムをそろえられる
蜂の巣の駆除に必要なアイテムは次のとおりです。
必要なアイテム
・防護服 or 防護服相当のウェア
・蜂用殺虫スプレー2本
・蜂用の忌避剤スプレー
・赤いライト
・二重にしたゴミ袋
・ほうき・ちりとり・トング
防護服は購入するとなると数万円~10万円以上かかるため、毎年必ず巣が作られるというケースでなければ、手持ちのウェアを組み合わせて防護服相当の重装備にするのが一般的です。
蜂用殺虫スプレーは2本用意しましょう。巣の大きさや場所によっては1本で足りる場合もありますが、噴射量が足りないと蜂を駆除しきれない恐れがあるからです。刺激によって興奮した蜂が刺してくることがあります。
その他のアイテムを含めた詳細は、次の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
こちらもCHECK
-

-
自分で蜂を駆除するのに必要なものは?防護服がないときの対処法も
蜂駆除を自分でおこなうためには、しっかりした準備が必要です。しかし、蜂駆除の経験が豊富な人は少ないため、何をそろえれば良いのかわからず、着手をためらっている人も多いのではないでしょうか。 そこで本記事 ...
続きを見る
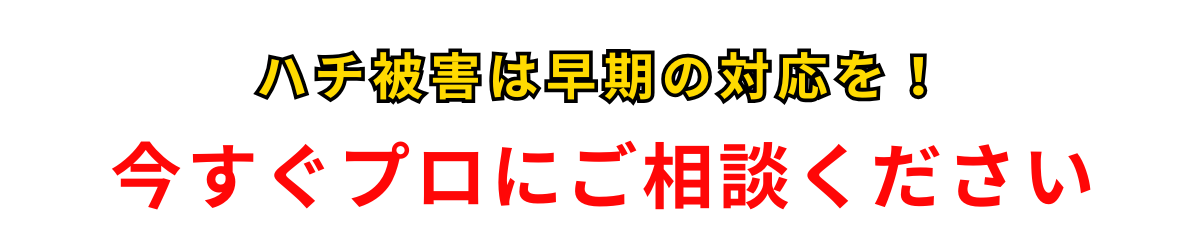
賃貸物件なら大家・管理会社に相談

アパートやマンションなどの集合住宅・賃貸物件の場合、ベランダは共有部分です。しかし、災害時を除いては部屋の借主以外は使わないため、蜂駆除の責任が貸主と借主のどちらになるかは賃貸借契約の内容によって異なります。一般的には借主の責任によって駆除するものとされていますが、念のため契約書を確認しておきましょう。
また、責任所在が借主にある場合でも、業者への依頼も含めて自分で対処するのが難しい状況であれば、放置せずに大家・管理会社へ連絡することが大切です。他の住民が刺されるリスクがあるため、報告しないことで責任を問われる可能性があります。詳しくは次の記事をご覧ください。
こちらもCHECK
-

-
蜂の巣がアパートにできたら大家さん・管理会社に連絡!理由を解説
アパートやマンションなどの賃貸物件で蜂の巣ができたときは、大家さんや管理会社の存在もあるため、どう対処すべきか迷うことがあるでしょう。結論からいえば、巣ができた場所によって対処すべき人が異なります。し ...
続きを見る
ベランダの蜂対策を把握しておこう
ベランダに蜂が飛来するシーズンは、窓の開け閉めや洗濯物の取り込みに注意が必要です。室内に入れてしまわないように、しっかり確認しましょう。甘い香りがするものの撤去や忌避剤。・防虫ネットで寄り付きを防ぐことも大切です。
なお、蜂を発見したときは大声を出さず、静かに行動することを心掛けましょう。蜂を刺激せずに室内へ避難し、落ち着いてから対策をすることをおすすめします。
ただし、蜂の巣を自分で駆除できるかどうかは、状況によって異なります。脚立を使用しなければいけない場合や巣の規模が大きい場合は、必ず蜂駆除業者に相談してください。賃貸の場合は大家さんや管理会社への相談も大切です。
よくある質問
ベランダで蜂の巣を見つけたらまずどうすればいい?
まずは静かに距離をとり、室内に戻って窓を閉めてください。その上で室内から蜂の行動を観察し、巣の場所を特定、あたりをつけましょう。
ベランダに蜂がくる理由は?
雨風をしのげる屋根や壁があること、花のプランターや柔軟剤の香りなど、エサ場と認識しやすい甘い香りがすることが要因です。
ベランダの蜂の巣を予防する方法はある?
忌避剤の散布や防虫ネットの設置がおすすめです。また、蜂が活発な時期は花のプランターを室内に入れる、柔軟剤を無香料のタイプに変えるなどの対策も有用です。
賃貸のベランダに蜂が出たときはどうする?
まずはベランダから退避して窓を閉め、管理会社か大家さんに連絡してください。隣人の安全にも影響するため、管理会社や大家さんに連絡することで周知してもらえます。駆除の責任者に関しては賃貸契約によるので、連絡したときに相談しましょう。





