マルハナバチは「飛ぶぬいぐるみ」と呼ばれるほど、ふわふわの毛が生えた可愛らしい蜂です。養蜂されるミツバチと同じミツバチ科に属しており、植物の受粉を助ける益虫といえます。
本記事では日本に生息する16種類のマルハナバチの見た目や性格、特徴を詳しく解説します。分布や見られる時期も掲載しているので、ぜひ観察の参考にしてください。

目次
マルハナバチ属16種類の一覧

マルハナバチは、ハチ目ミツバチ科ミツバチ亜科(マルハナバチ亜科)に分類されます。
| 種類 | 見られる時期 | 分布 |
| トラマルハナバチ | 4月下旬~10月 | 日本に広く分布 |
| コマルハナバチ | 3~7月 | 日本に広く分布 |
| クロマルハナバチ | 4~10月 | 本州 |
| オオマルハナバチ | 4月中旬~10月 | 日本に広く分布 |
| ミヤママルハナバチ | 5~10月 | 標高の高い場所、北海道 |
| ヒメマルハナバチ | 5~10月 | 標高の高い場所 |
| ニセハイイロマルハナバチ | 5月下旬~10月 | 北海道、東北 |
| ハイイロマルハナバチ | 5月下旬~10月 | 北海道、本州の一部 |
| ニッポンヤドリマルハナバチ | 6~9月 | 本州の一部 |
| ウスリーマルハナバチ | 5~10月 | 本州の一部 |
| ナガマルハナバチ | 5月下旬~9月 | 本州の一部 |
| エゾナガマルハナバチ | 6~9月 | 北海道 |
| シュレンクマルハナバチ | 5月中旬~9月 | 北海道 |
| アカマルハナバチ | 4月中旬~8月 | 北海道 |
| ノサップマルハナバチ | 6~9月 | 北海道 |
| セイヨウオオマルハナバチ | 5~10月 | 北海道、本州 |
以下ではマルハナバチの種類ごとに、見た目や特性を解説します。
トラマルハナバチ

| 和名 | トラマルハナバチ |
| 学名 | Bombus diversus |
| 見られる時期 | 4月下旬~10月 |
| 体長 | 12~20mm |
| 見た目の特徴 | 黄褐色のふわふわの毛 虎のような黒の縞模様 顔が長い(ナガマルハナバチ亜種) |
| 分布 | 本州、四国、九州、対馬 |
見た目
トラマルハナバチは栗色・黄褐色のふわふわの毛と虎のような黒い縞模様が特徴のマルハナバチです。
後述するナガマルハナバチやウスリーマルハナバチと同様にナガマルハナバチ亜種に分類される蜂で、顔(頭部)が長いという特徴もあります。
性格・特性
攻撃性はマルハナバチにしてはやや強めで、巣を刺激すると刺されることがあります。昼間に活動し、飛ぶ動きが素早いことも特徴です。
発生は年1回、4月下旬に女王蜂が冬眠から目覚めて産卵し、6月に働き蜂が羽化します。雄と新女王蜂の誕生は8月下旬から10月です。冬眠に入るのは10月末が中心ですが、地域によっては11月上旬でも見かけることがあるでしょう。
毒量・毒性
毒性は強くありません。刺された場合は痛みを伴いますが、アレルギーがなければ大きな健康被害には至らないケースが多いようです。
巣の特徴
平地から低山の森・林に生息し、野ネズミの古い巣などを活用して地中の空間に巣を作ります。巣の規模は大きく、繭の数は400~1,300個になることもあります。巣の上には保温用のワックスをかけるのが特徴です。
コマルハナバチ

※画像はイメージ
| 和名 | コマルハナバチ |
| 学名 | Bombus ardens |
| 見られる時期 | 3~7月 |
| 体長 | 8~16mm |
| 見た目の特徴 | 全身ふわふわの毛 メス(働き蜂)は全体に黒くお尻だけオレンジ メスは腹部に黄色の線が入る個体もいる オスは全体が黄色でお尻だけオレンジ |
| 分布 | 北海道、本州、四国、九州 |
見た目
コマルハナバチは全身がふわふわの毛で覆われており、色はオスとメス(働き蜂)で大きく異なります。メスは全身が黒く、お尻だけがオレンジ色で、後述のクロマルハナバチにそっくりです。個体によっては腹部に黄色い線が入ることがあります。
一方のオスは全身に黄色のふわふわの毛が生えており、お尻だけがオレンジ色です。オスとメスで違う種類に見えるでしょう。なお、本州のマルハナバチの中でコマルハナバチは最小クラスです。
性格・特性
性格はおだやかで、人への攻撃性はほとんどありません。花粉や蜜を集めて暮らし、花の受粉に重要な役割を果たします。繁殖期の雄は、木の幹や葉にフェロモンで「匂いマーク」をつけ、巡回しながら雌との交尾を狙うという独特の行動をします。
巣の特徴
地面の中や木の隙間など、閉じた空間に巣を作ります。自分たちで巣をつくるだけでなく、鳥の巣箱を乗っ取ることもあるようです。ヤマガラやシジュウカラが使っていたコケや獣毛を再利用して、自分の巣を作るケースがあります。
クロマルハナバチ

| 和名 | クロマルハナバチ |
| 学名 | Bombus igunitus |
| 見られる時期 | 4~10月 |
| 体長 | 12~19mm |
| 見た目の特徴 | 全体的に黒い お尻はオレンジ オスは胸周りに黄色い毛 |
| 分布 | 本州、四国、九州、壱岐など一部の島(山地寄り) |
見た目
クロマルハナバチは体長12~19mm、全身が黒い毛に覆われ、お尻だけオレンジ色の配色です。女王蜂と働き蜂は似た色合いですが、雄は胸周りに黄色い毛が密集しています。
メス、オスの配色ともにコマルハナバチに似ていますが、クロマルハナバチの方がやや大きく、オスに関しては胸部と腹部に黒い縞模様がある点で異なります。
性格・特性
性格はおだやかで、人を刺すことはほとんどありません。5月から10月まで活動し、花の受粉に重要な役割を果たします。本州と一部の島に分布し、北海道や南西諸島にはいません。
巣の特徴
5月から10月にかけて地中の狭い空洞に巣を作ります。ネズミが使った古い巣や他のマルハナバチが巣をつくったことのある場所などです。自分の体からロウを出して巣を作り、花粉と蜜を集めて産卵します。
オオマルハナバチ
| 和名 | オオマルハナバチ |
| 学名 | Bombus hypocrita |
| 見られる時期 | 4月中旬~10月 |
| 体長 | 11~22mm |
| 見た目の特徴 | 腹部には黒と白と黄色の帯 お尻が黄色 |
| 分布 | 北海道、本州、四国、九州 |
見た目
エゾオオマルハナバチは11~22mmの体長です。腹部には黒と黄色と白の帯があり、セイヨウオオマルハナバチと似た外見をしています。見分けるポイントはお尻です。セイヨウオオマルハナバチはお尻の先端が白色ですが、エゾオオマルハナバチのお尻は黄色い毛で覆われています。体毛はふさふさしており、雌と雄で色の違いはあまり見られません。
性格・特性
平地から山地まで幅広い場所に生息し、春の早い時期から活動を始めます。市街地や庭の花にもよく訪れ、人目に触れる機会が多い蜂です。活動期間は長く、秋まで飛んでいる姿が見られます。個体数が多く、北海道で最もよく見られるマルハナバチの一つです。
巣の特徴
地中に巣を作り、冬は土の中で越冬します。日当たりがよく、柔らかい土を選んで越冬することがわかっています。春になると、女王蜂が目覚めて1匹で巣作りを始め、花粉や蜜を集めながら巣を広げていきます。
ミヤママルハナバチ
| 和名 | ミヤママルハナバチ |
| 学名 | Bombus honshuensis |
| 見られる時期 | 5~10月 |
| 体長 | 10~16mm |
| 見た目の特徴 | 胸の中央の毛は褐色 胸部側面と腹部の毛はレモンイエロー 腹部には黒の縞模様 |
| 分布 | 北海道~九州(山地、高原) |
見た目
ミヤママルハナバチはコマルハナバチと並んで、本州の中では最小クラスのマルハナバチです。
胸の中央の毛は赤みがかった褐色ですが、胸部側面と腹部にはレモンイエローの毛が生えています。また、腹部には黒の縞模様があるのも特徴です。
性格・特性
他のマルハナバチと比べても威嚇行動が少なく、おだやかな性質です。刺激を受けると「擬死」と呼ばれる行動をとり、数分間じっと動かなくなることがあります。ミヤママルハナバチは本州の標高200~2,500mの山地が生息地です。さまざまな植物から花粉や蜜を集めます。
巣の特徴
地面の中や木のすき間に巣を作ります。飼育下では、女王蜂が体からワックスを出し、柔らかい蜜壺を作って底に卵室を作ります。巣は小さめで、働き蜂や雄蜂の数も少なめです。刺激があると、女王蜂が一時的に巣を離れることもあります。
ヒメマルハナバチ
| 和名 | ヒメマルハナバチ |
| 学名 | Bombus beaticola |
| 見られる時期 | 5~10月 |
| 体長 | 9~16mm |
| 見た目の特徴 | 全体に淡い色味のふわふわとした体毛 腹は黄色と黒の縞模様 |
| 分布 | 標高の高い場所 |
見た目
ヒメマルハナバチは体長9~16mmです。全体に淡い色味のふわふわとした体毛が生えています。腹には黄色と黒の縞模様があります。
性格・特性
性格はおだやかで、人に対して攻撃することはほとんどありません。標高が高い場所を好み、5月から10月に活動します。花を訪れて花粉や蜜を集める様子がよく見られます。特に秋は目撃されやすく、観察の機会が増えます。
ニセハイイロマルハナバチ
| 和名 | ニセハイイロマルハナバチ |
| 学名 | Bombus pseudobaicalensis |
| 見られる時期 | 5月下旬~10月 |
| 体長 | 11~18mm |
| 見た目の特徴 | 腹に黒と灰色の縞模様 全身に黄色みがかった灰色の毛 |
| 分布 | 北海道、青森、岩手 |
見た目
ニセハイイロマルハナバチは体長11〜18mmです。体は灰白色の長い毛で覆われています。腹にははっきりした縞模様が見られます。近縁のハイイロマルハナバチとの違いは、腹の第2節側面に黒い毛が少ない点です。雄の触角はギザギザ状で、これも見分けるポイントです。
性格・特性
性格はおだやかで、人を攻撃することはほとんどなく、観察しやすいハチです。草原に生息する種で、北海道や東北の平地でよく見られます。マメ科などの花から花粉や蜜を集め、春から秋にかけて活動します。特に花が多い時期に活発です。
巣の特徴
地面や土の中に巣を作り、自然のくぼみや動物の古い巣を利用します。草原のような開けた場所が好みです。越冬時には日当たりがよく、柔らかい土の斜面上部を巣作りの場所に選びます。
ハイイロマルハナバチ
| 和名 | ハイイロマルハナバチ |
| 学名 | Bombus deuteronymus |
| 見られる時期 | 5月下旬~10月 |
| 体長 | 15~18mm |
| 見た目の特徴 | 腹に黒と灰色の縞模様 全身に黄色みがかった灰色の毛 |
| 分布 | 北海道、本州の一部 |
見た目
ハイイロマルハナバチは、15~18mmです。全身が黄みがかった灰色の毛で覆われています。また腹には黒と灰色の縞模様があります。
性格・特性
ハイイロマルハナバチは長野県や山梨県など、本州中北部の高地に分布する蜂です。春から秋にかけて花々を回り、蜜や花粉を集めます。活動は4~10月で、雄は秋に現れます。
巣の特徴
巣はなかなか見つかりませんが、地中や草原で小規模の巣を作るようです。花粉ポケットで幼虫に餌を与え、蜜壺で蜜をためます。材料となる蜜蝋の量は少なく、限られた材料で巣を作ります。
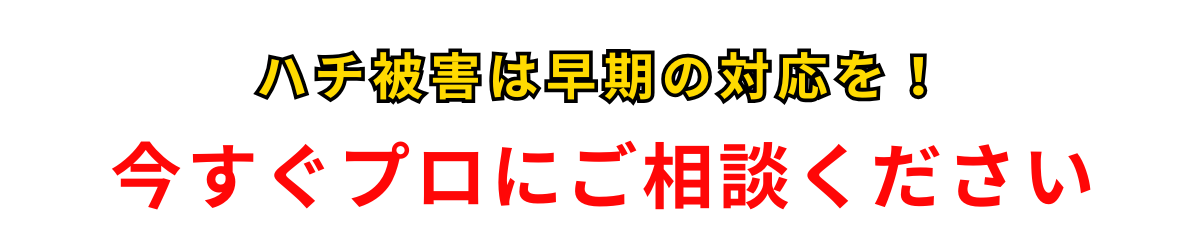
ニッポンヤドリマルハナバチ
| 和名 | ニッポンヤドリマルハナバチ |
| 学名 | Bombus norvegicus japonicus |
| 見られる時期 | 6~9月 |
| 体長 | 12~20mm |
| 見た目の特徴 | 淡黄色の毛 毛がまばらでふわふわ感が少ない |
| 分布 | 本州の一部 |
見た目
マルハナバチの中では毛がまばらで、ふわふわ感のない見た目をしています。この特徴は、ニッポンヤドリマルハナバチの寄生性にあります。
ヒメマルハナバチの巣に寄生して産卵し、ヒメマルハナバチに子育てしてもらうため、自分で花粉を集める必要がありません。そのため、毛が衰退したと考えられます。
性格・特性
ニッポンヤドリマルハナバチは個体数が少なく、分布域も狭い希少種です。長野県には生息している記録がありますが、広範囲の調査でもみつからなかったことがあるなど、詳細な分布域はわかっていないようです。
巣の特徴
ヒメマルハナバチの巣を乗っ取るため、自分で作った巣は存在しません。また、子育てする必要がないので働き蜂はおらず、女王蜂とオス蜂だけが生まれます。
ウスリーマルハナバチ
| 和名 | ウスリーマルハナバチ |
| 学名 | Bombus ussurensis |
| 見られる時期 | 4月下旬~10月 |
| 体長 | 不明 |
| 見た目の特徴 | トラマルハナバチに似ている 毛がやや緑がかっている 黒い縞模様が目立つ |
| 分布 | 本州の一部 |
見た目
全体像はトラマルハナバチに似ていますが、毛の色はやや緑がかっており、黒い縞模様が目立つのが特徴です。
性格・特性
栃木県では絶滅危惧I類(Aランク)に指定、長野県では絶滅危惧Ⅱ類に指定されている希少種です。富山県では山地で少数が確認されており、基本的には標高700~2,000mの山林や高山の草地を好むとされています。
ナガマルハナバチ
| 和名 | ナガマルハナバチ |
| 学名 | Bombus consobrinus |
| 見られる時期 | 5月下旬~9月 |
| 体長 | 不明 |
| 見た目の特徴 | トラマルハナバチに似ている 毛が薄く、腹背節だけ長毛でボサボサ 顔が長い |
| 分布 | 東北南部から中部山岳地帯 |
見た目
ナガマルハナバチは顔(頭部)の長いナガマルハナバチ亜種の代表的な種類です。ただし、分布域が狭く個体数の少ない希少種とされています。
全体的にはトラマルハナバチに似ていますが、毛の色はやや緑がかっており、生え具合は薄めです。腹背部だけ毛が長く、ボサボサして見えます。
巣の特徴
ネズミの穴や自然にできた坑道に巣作りします。コロニーはあまり大きくないようです。腹部から分泌するロウで部屋や壺をつくり、産卵や蜜・花粉の貯蔵をおこないます。
エゾナガマルハナバチ
| 和名 | エゾナガマルハナバチ |
| 学名 | Bombus yezoensis |
| 見られる時期 | 6~9月 |
| 体長 | 不明 |
| 見た目の特徴 | 黄色がかった灰色の毛 黒い縞模様 顔が長い |
| 分布 | 北海道 |
見た目
小さい個体はヒメマルハナバチの働き蜂に似ています。黄色がかった灰色の毛と黒の毛の縞模様に、長い顔が特徴です。
性格・特性
分布は北海道のみで、生息域は山地から高山帯に限られます。雪潤草原(高茎草原)では、チシマアザミやトリカブトなどの植物を好むとされています。
シュレンクマルハナバチ
| 和名 | シュレンクマルハナバチ |
| 学名 | BBombus schrencki |
| 見られる時期 | 5月中旬~9月 |
| 体長 | 10~20mm |
| 見た目の特徴 | 側面と腹部に淡黄色の毛 胸部はオレンジの毛 腹部の黒い縞模様はややはっきり トラマルハナバチやミヤママルハナバチに似ている |
| 分布 | 本北海道 |
見た目
側面と腹部は淡い黄色、胸部は赤みの強いオレンジ色の毛が生えたマルハナバチです。
トラマルハナバチやミヤママルハナバチに似ていますが、お尻は淡黄色という点で違いがあります。また、ミヤママルハナバチにも似ていますが、分布が異なるため見分けられるでしょう。
性格・特性
北海道固有の亜種で、石狩平野から東部の平地から山地に生息しています。北海道以外では見られません。
アカマルハナバチ

| 和名 | アカマルハナバチ |
| 学名 | Bombus hypnorum |
| 見られる時期 | 4月中旬~8月 |
| 体長 | 10~20mm |
| 見た目の特徴 | 胸~腹部中間まで赤褐色の毛 腹部中間は黒 お尻は白 |
| 分布 | 北海道 |
見た目
アカマルハナバチは体長10~20mmです。胸~腹部中間の赤褐色の毛が特徴で、腹部中間は黒、お尻は白の配色です。
性格・特性
北海道だけに生息するマルハナバチの亜種です。雪潤草原から高根ヶ原などに現れ、エゾツツジやコケモモを好みます。振動によって花粉を集める行動「バズフォージング(buzz foraging)」が観察されています。
ノサップマルハナバチ
| 和名 | ノサップマルハナバチ |
| 学名 | Bombus florilegus |
| 見られる時期 | 6~9月 |
| 体長 | 不明 |
| 見た目の特徴 | 白(淡黄色)と黒のパンダのような配色 セイヨウオオマルハナバチに似ている |
| 分布 | 北海道 |
見た目
白に近い淡黄色と黒で、それぞれの色の帯が太いためパンダのような配色のマルハナバチです。顔は短く、全体的にコロンと丸いフォルムに見えます。
フォルムや配色の幅はセイヨウオオマルハナバチに似ていますが、黄色よりも白に近い帯なので見分けられるでしょう。
性格・特性
動きがすばやく警戒心が強いようです。北海道の沿岸部(根室半島・野付半島・知床半島)の平地にのみに生息する希少種で、環境省のレッドリストでは準絶滅危惧種に指定されています。
セイヨウオオマルハナバチ

| 和名 | セイヨウオオマルハナバチ |
| 学名 | Bombus terrestris |
| 見られる時期 | 5~10月 |
| 体長 | 10~20mm |
| 見た目の特徴 | 腹部には黒と白と黄色の帯 お尻が白色 |
| 分布 | 北海道、本州 |
見た目
セイヨウオオマルハナバチは体長10~20mmです。黒い体に黄色の帯があります。エゾオオマルハナバチに似ていますが、お尻の先端が白く、翅が茶色っぽく見えるのが特徴です。
性格・特性
セイヨウオオマルハナバチは日本に生息していますが外来種です。ヨーロッパ原産で、1991年にトマトやナスなどの受粉のため日本に導入されました。
現在は野外に定着し、在来のマルハナバチに悪影響を与えています。在来種の餌や巣の場所を奪うので、生態系への影響が大きい蜂です。2006年に「特定外来生物」に指定され、輸入や飼育などは原則禁止です。北海道では駆除も行われています。
巣の特徴
セイヨウオオマルハナバチの巣は、1つの巣に複数の女王蜂がいる「多雌性」です。そのため、短期間で多くの働き蜂が育ちます。巣を作る場所は地面の中、建物のすき間、草地などさまざまです。
個性豊かなマルハナバチたちをもっと身近に感じよう
日本に生息するマルハナバチ16種をご紹介しました。それぞれが異なる見た目や暮らし方を持ち、毛の色や模様、行動の違いもさまざまです。共通しているのはおだやかな性格で、人を刺すことはほとんどありません。
花とともに生きる姿は、身近な自然を魅力的に見せてくれます。気になる種類があれば、ぜひ身の回りで探してみてください。いつもの風景が、ちょっと変わって見えるかもしれません。
よくある質問
マルハナバチは人にとって危険ですか?
スズメバチよりはるかに安全です。
マルハナバチとミツバチの違いは何ですか?
マルハナバチは丸く毛深い。ミツバチより小さな群れです。
マルハナバチを自宅の庭で見かけたらどうすればいいですか?
基本は放置でOKです。巣が近くにある場合のみ注意。





